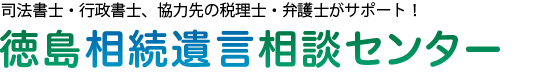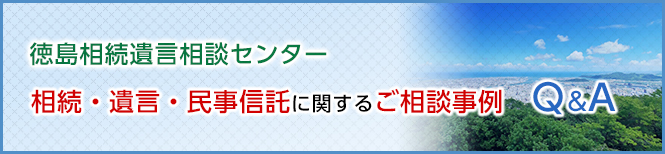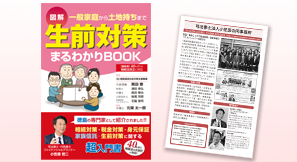2019年11月16日
Q:晩年の母を介護してくれていた叔母に遺産相続してほしいです。(徳島)
徳島で叔母と同居していた母が、病気で先月亡くなりました。叔母は母の妹にあたります。一人娘の私は徳島県外へ巣立っており、母は父に先立たれたあとは一人で暮らしていました。その後、母に病気が見つかり通院や介護、身の回りの世話が必要になりましたが、私には家庭もあり徳島からは遠いところに住んでいますので、徳島に住んでいた叔母が介護を引き受けてくれ、10年ほど同居しながら世話をお願いしていました。
母には預金の他に大きな資産はなく、叔母には今まで何のお礼もできていません。申し訳程度なのですが、せめて、叔母に母の預金を渡したいと思っています。叔母には当初、遺産相続は全然考えていないと言われましたが、介護の件で本当に感謝しているのでぜひ遺産を受け取ってほしいと言うと、ありがたくお受けしますとの返事をもらいました。しかし、そもそも叔母は法定相続人ではありませんし、母が遺言を残したわけでもありません。叔母に遺産を受け取ってもらうことはできるのでしょうか?(徳島)
A:遺産相続ではなく、特別寄与料として渡すことができる可能性があります。
遺産相続には寄与分という制度があります。これは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加について特別な寄与をした相続人に、その寄与した分を遺産相続に反映させることで、相続人間の公平性を図るための制度です。この制度は相続人以外(例えば被相続人の子の配偶者など)には認められていませんでした。ご相談者様のケースでもお母様の相続人はご相談者様だけとなりますので、叔母様にはこの制度が認められません。このように、相続人ではない親族の被相続人の寄与に配慮するため、平成30年の法改正により「特別寄与料の請求権」が設けられ、相続人の親族は特別寄与料を請求できるようになりました。
特別寄与料とは、被相続人の財産の増加や維持に寄与(貢献)した程度を指します。具体的にはご相談者様の叔母様のように生前に被相続人の看護や介護をする、事業の手伝いを無給で行う、といったことなどが挙げられます。もし叔母様が介護をしていなかったとしたら、お母様は介護療養型医療施設などに入院する必要があったと推測されます。そのための費用を、10年間叔母様が介護したことによって節約した、つまりお母様の財産の減少を防いだと考えられ、「特別寄与料」と認められる可能性があります。しかし、特に療養看護など金銭以外での貢献は客観的に判断しづらいため、特別寄与料と認められるかどうかは遺産相続に精通した専門家に事前にご相談いただくことをお勧め致します。その際には診断書やカルテ、介護にかかった費用の分かる領収証などがあるとより安心です。なお、この特別寄与料の支払いについては、当事者間で話がまとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
疑問や不安なことが多い遺産相続では、後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することは大変有効です。
当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。
2019年11月08日
Q:友人に遺産を渡したい場合にはどのように相続の準備をすればよいでしょうか。(徳島)
私は今年70歳になりますが、独身で子どももいません。徳島に暮らして25年になりますが、近隣の方々と交流する機会が多く、親しい友人も数人できました。その友人たちは、私が困った際には助けになってくれました。
私は最近終活について悩んでおりますので、今回ご相談いたしました。私の両親はすでに亡くなっており、唯一の家族となる兄とは、実家のある大阪から徳島に出てきてからは長らく連絡を取っていません。私が亡くなった場合には、私の遺産は兄が1人で相続することになると思います。しかし、私は疎遠である兄ではなく、徳島での暮らしで私の助けになってくれた友人たちに私の遺産を渡したいと考えています。このような場合には、どのように相続に関する準備をすればよいでしょうか。(徳島)
A:相続の準備として、ご友人に遺産を渡す旨の遺言を公正証書遺言で作成しておきましょう。
この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
民法によって定められた相続人であるお兄様ではなく、徳島での暮らしを助けてくれたご友人に遺産を渡したいとお考えでしたら、その旨を記載した公正証書遺言を作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書の中のひとつで、確実に遺言を残したい場合に有効な遺言書の種類です。公証役場で、遺言を残す本人(遺言者)と一緒に遺言の内容を公証人が確認して作成し、公証役場に、作成した遺言書の原本が保管されます。したがって、遺言書の紛失や改変の危険がなく、遺言書の内容を確実に実現することが期待できます。
また、法定相続人以外に遺産を渡す内容の遺言書を作成する場合には「遺留分」に注意しなければなりません。法定相続人以外に、財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、一部の法定相続人にとっては、遺留分という最低限相続できる財産の割合を侵害されていることになってしまいます。民法では、そのような場合に侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求することができると定めています。これは「遺留分侵害額請求権」という法定相続人がすべての相続財産を受け取ることができず、生活が難しい状況になってしまうようなことを防ぐための権利です。
ただし、遺留分を持つ相続人は亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、今回のご相談者様の場合は遺留分侵害額の請求をされることはありませんので、ご友人に遺産を渡す意思を遺言書に記すことでご相談者様のお考えを実現することができるでしょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続のお手続きに実績のある専門家がご相談に無料でご対応しております。徳島近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。
2019年11月01日
Q:事実婚の女性に遺言書を残して財産を渡したいのですが、どうしたらいいでしょうか?(徳島)
私は徳島に住む、現在は年金暮らしの70代の男性です。現役のころは会社を営んでおりましたが、5、6年前に経営権を譲っております。今は、軽い持病はありますが事実婚の10歳以上年の離れた妻とのんびりとした余生を送っています。私は20年以上前に妻を亡くしており、亡くなった妻との間に同じく徳島に住む子供が一人おります。事実婚の妻が法的に後妻となることで子供との関係がこじれるのが心配で、今までずっと籍を入れずにきてしまいました。私の亡き後も妻と子供には仲良くやっていってほしいと思っています。現在の妻には大変世話になっており、籍を入れていないというだけで妻には変わりありません。このまま私が亡くなると事実婚である妻には財産を渡すことが出来ず、どうにかならないものかと調べたところ、遺言書を残すといいと教えて頂きました。私に何かあってからでは遅いので早急に遺言書を作りたいと思っていますが、確実に妻に財産を渡すためにはどのような遺言書を作成すべきでしょうか?(徳島)
A:事実婚の奥様とお子様が将来争わない為にも公正証書で遺言書を作りましょう。
遺言書を残さなかった場合、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様の亡き後、相続権はご相談者様のお子様のみになってしまいます。事実婚である現在の奥様には相続権はないのです。しかしながら法的に有効な遺言書を作成し、きちんと保管しておけば“遺贈”という形で今の奥様に財産を残すことができますのでご安心ください。
遺言書を作成するにあたっていくつか大事な点があります。まず遺言書の種類を簡単にご説明いたします。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。ただし遺言の方式を守らないと無効。現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用が掛かる。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。
ご相談者様のケースの場合、遺言書をお子様に預けることは避けた方が良いので、②の公正証書遺言を作ることをお勧めします。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、作成時に公証人によって文案が確認されます。また併せて遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が権利を持って、遺言の内容通りに財産を分割してくれるので安心です。ご相談者様が亡くなった後、奥様が手続きやお子様とのやり取りに戸惑うこともないでしょう。
なお遺言書を作成する際に配慮していただきたいのは“遺留分”です。“遺留分”とは、一部の相続人に認められている、民法で保障されている相続財産の最低限度の取り分のことです。ご相談者様のお子様は直系卑属にあたりますので、遺留分があります。もしご相談者様が遺言書の内容を「全財産を奥様に遺贈する」とすると、お子様はご相談者様の奥様に遺留分を渡すようにと、調停等をおこすことが考えられます。そうなると、ご相談者様が望んでいないであろう“奥様とお子様の争い”を起こす結果になりかねません。そのような事態を避けるためにも、遺言書を作る時点で遺留分より多くの財産をお子様に残すことをお勧めします。
有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。
18 / 22«...10...1617181920...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。